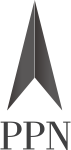俳人 長谷川櫂
経歴
熊本生まれ
1976年 東京大学法学部卒業
読売新聞社入社(2000年退社)
1979年 飴山實に師事
1992年 東海大学文芸創作学科特任教授(2019年まで)
1993年「古志」主宰(2010年まで)
2000年 朝日新聞俳壇選者(現在まで)
2004年 読売新聞に詩歌コラム「四季」を連載開始
2007年 (財)神奈川文学振興会評議員(2011年理事、2012年副理事長、現在まで ※現在は公益財団法人)
2008年 インターネット歳時記「きごさい」代表(現在まで)
2012年 奥の細道文学賞最終選考委員(現在まで)
2012年 ドナルド・キーン賞最終選考委員(現在まで)
2013年 NHK 「100分de名著」特別版「松尾芭蕉 おくのほそ道」放送
2016年 NHK 「課外授業 ようこそ先輩」放送
賞歴
1990年『俳句の宇宙』サントリー学芸賞芸術・文学部門受賞
2003年 句集『虚空』読売文学賞詩歌俳句賞
2023年 神奈川文化賞
2025年 日本芸術院賞
著書
公式サイトよりご覧ください。

阿久津 貴史
PPN代表,元パワーリフティング選手。2012年に日本記録を樹立し初優勝して以来,12連覇を達成。2023年の世界大会を最後に現役を引退。
また初優勝の年に,日本人のメンタル・フィジカル・スキルの3要素を極限のレベルに高めるという想いを形にすべく、東京都練馬区豊玉北にパワーリフティングジム「Team X-treme Power!!!」(TXP)を設立し、選手が成長しやすい環境作りにも尽力している。現在TXPは国内の主要4大大会で団体優勝を22回達成(2025年時点)
パワーリフティング競技の普及のため,2020年から日本パワーリフティング協会アスリート委員の委員長,NPO法人東京都パワーリフティング協会の副理事長にも就任し組織運営と大会運営に精力的に携わっている。
2024年からは「人間の持つあらゆる能力をいかに高めるか?」という個人的な探究のため,プライベートで東京都立大学大学院知覚運動制御研究室で研究生活をスタート。NSCA-CSCS・NSCA-CPT(20年以上保持者)/認定スポーツメンタルコーチ
阿久津:長谷川さん,長年お世話になっております。この度はインタビューへのご協力を誠に有難うございます。
このトップランナーインタビューは何かの目標や夢に向かって生きている全ての方に向けて,あらゆる業界で活躍している人の「魂の叫び」をお届けするシリーズとしてやらせていただいております。
本日は,長谷川さんが歩んでこられた道,そうした中から生まれた「魂の叫び」をお聞かせいただければ幸いです。
長谷川さんはご職業といっていいのかわかりませんが「俳人」という普段あまり聞きなれない肩書き(お仕事)をされていますよね。もし可能であればそのあたりを含めて簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか?
長谷川さん:「俳人」は広い意味では「俳句を作りつづけている人」です。この意味の俳人は日本には巨人軍のファンの数と同じくらいいます。日本は多くの人が俳句や短歌といった詩を作る「不思議の国」です。
でも狭い意味では「俳人」は「俳句で食べていける人」です。この意味の俳人はいつの時代も数人しかいません。夫や妻の収入、親の財産で生活しながら俳句を作っている人は俳人ではありません。
私は若いころから俳句を作ってきましたが、46歳(2000年)の夏に読売新聞の記者を辞めて俳句だけで生きてゆくことにしました。この時点で広い意味の「俳人」から狭い意味の「俳人」になったことになります。
阿久津:有難うございます。俳句や短歌を愉しまれている人が日本にはたくさんいらっしゃるのですね。そして「俳人」の意味に関しましても詳しいご説明有難うございます。俳句を仕事にできるプロフェッショナルな人,ということなのですね。俳人の道を選ばれた際のお話はまた後でゆっくりお聞かせください。
まず原点といいますか,長谷川さんは俳句にいつ頃からご興味があったのですか?
言葉っておもしろいな

長谷川さん:中学生(熊本県宇城市)のころ、ある国語の先生がいて「言葉っておもしろいな」と思ったのがはじまりです。そのときはまだ俳句に焦点を絞ってなかったのですが、いろんな本を読んでゆくうち、俳句は短いだけに言葉のおもしろさが凝縮していることに気づきした。
そんなわけで俳句を真剣に作るようになったのは、20歳ころからです。阿久津:そうだったのですね。「言葉っておもしろいな」と長谷川さんが感じる授業をされた先生,素敵ですね。
俳人の道を選ばれた際のお話についてお聞かせいただけますでしょうか。2000年に読売新聞社を退社されて完全にフリーの俳人になることを決められた時はどのような心境だったのでしょうか?46歳というご年齢で一般的にはなかなかできない決断と感じています。
俳句で生きてゆくんだ
長谷川さん:当時、高校生の長男と中学生の長女がいましたので、一家4人どうやって食べていくか、これは大問題だったはずです。

会社を辞めるのは大変ですよね。給料だけでなく医療保険やそのほか、会社に丸抱えで目に見えない恩恵を受けているからです。お金の問題を考えはじめると、たぶん辞められないと思います。
ただ会社を辞めたことで、これからは「俳句で生きてゆくんだ」という覚悟ができて、その後、大いに力になりました。「後へは退けない、ここで頑張らないといけない」ということですね。これが私にとって会社を辞めて、いちばんよかったことです。
阿久津:有難うございます。「大問題だったはず」という表現に,長谷川さんには目の前の広がる違う景色の方が鮮明に見えていたのかなぁと勝手ながら想像してしまいました。
会社を辞めていちばんよかった理由に「後ろへは退けない状況になった」ことをあげられたのは,大先輩の長谷川さんに失礼を承知で,長谷川さんらしいなと感じました。長年お話しさせていただいている中で実はふとしたところに長谷川さんの熱い部分を感じております。
長谷川さんは俳句に関する作品を作るだけでなく,俳句結社「古志」の創刊,読売新聞に詩歌コラム「四季」の連載開始,プライベートサイト「一億人の俳句入門」で「ネット投句」「うたたね歌仙」の主宰など常に新しいことに挑戦されている印象です。その点についてどのような想いがあるのかなど長谷川さんのお考えをお聞かせいただくことは可能でしょうか?
長谷川さん:会社を辞めて、俳句に人生を賭けているのですから、たくさん「俳句の仕事」をするのは、むしろ当然のことです。だから、できるだけ「俳句の仕事」がしたいのです。
いろいろ仕事をして気づいたことが一つあって、それは「時間は伸縮自在」ということです。誰にとっても1日は24時間ですが、これは使い方によっては2倍にも3倍にもなります。50代の10年間はそんなふうでした。
逆にいえば、使い方を誤れば1日が半分、3分の1になってしまうということです。もしそうなると、私にとっては会社を辞めた意味がありません。
阿久津:時間は伸縮自在で使い方によって2倍にも3倍にもなる,というお言葉に「没頭できる状態(フロー)」を長期にわたってご経験されている印象を受けました。「できるだけ俳句の仕事がしたい」というお言葉に表れているように原点には「好きなこと」があるのだろうと感じました。
この流れで,時間軸に関わる質問をさせてください。読売新聞に掲載されている「四季」に関して,2004年4月1日から連載を開始されて7500回以上,一度の中断も代理執筆もなく、毎日続けられているということを知りました。20年以上にわたって休まず連載を続けられるって相当な覚悟がないとできないことだと思います。どのようなお気持ちで連載を続けられているのでしょうか?
1日を生きる小さな力になれたら
長谷川さん:読売新聞でいちばんの長期連載は植田まさしさんの四コマ漫画「コボちゃん」で15000回を超えています。「四季」はまだその半分ですが、俳句や短歌のコラムが新聞に毎日載るのはおそらく日本だけの現象ではないかと思います。
書きながら思うのは毎朝読んでくだる方々にとって、1日を生きる小さな力になれたらということです。

阿久津:ご継続されてこられている原点に「1日を生きる小さな力になれたら」というお気持ちがあるんですね。率直に素敵なお考えだなぁと感じました。私は俳句に関して全くの門外漢ですが,長谷川さんの四季での解説を拝読しますと「こんな視点があるのか」と考えさせられ実際に勇気をもらえます。
そして改めまして先日は日本芸術院賞の受賞,本当におめでとうございます。

長谷川さん:この賞をいただいて、これまでお世話になった方々に感謝しています。授賞式の午後、天皇皇后両陛下には皇居でのお茶にお招きいただき、御所の「しずかさ」にたいへん感銘を受けました。
どの賞でも「これまでご苦労さん」ではなくて「もっといい仕事をしなさい」という励ましであり、将来の仕事の前祝いだと思っていきましたので、いよいよ「俳句の仕事」に励みたいと思います。

阿久津:長谷川さんはたくさんの仕事をこなされていて超がつくほどの過密スケジュールかと思います(今年もすでに『四季のうた ウクライナの琴』中公文庫,『「おくのほそ道」を読む 決定版』ちくま文庫,を出版)。
そのような中でもトレーニングを週に4-5回継続的にこなされてますよね。かなりトレーニングフリークだと思ってます。トレーニング自体は何歳くらいからされているのですか?トレーニングノートは第2の句帳
大学生になって、このままではいけないと水泳とトレーニングをこっそりはじめました。できたばかりの髙田馬場のBIGBOXのトレーニングルームとプールに通いました。そこで早稲田大学でトレーニング学を研究しておられた窪田登先生とたまにお会いして、トレーニングのこつを教えてもらったこともあります。得難い体験でしょう?
それ以来、水泳をずっとやっていて、40代になって鎌倉の材木座でヨットの練習をはじめました。ところがヨットは海に出ると1日中、陸に帰れませんので時間のやりくりができなくなって、トレーニングだけにしました。
そのころまだ見よう見まねの我流でしたが、2013年から阿久津さんにご指導していただいています。もっと早く指導していただいていたらよかったと思います。体を動かすのは脳にもいいらしく、一石二鳥というか、不思議なことにトレーニング中は次々に俳句ができます。私のトレーニング・ノートには俳句がたくさん書いてあります。もはや「第2の句帳」ですね。
阿久津:年少期にそのようなご体験をされていたのですね。長谷川さんと初めてお会いした時には長谷川さんは既にかっこいい身体をされていたのでさぞスポーツマンなのだろうと思っていました。
窪田登先生から直接トレーニングを教わったご経験をお持ちだったのですね。衝撃です。それを知っていたら長谷川さんのトレーニングをみさせていただくのをお断りしていたかもしれません。笑
もうただただ恐縮です。
「トレーニング中に俳句が次々に浮かぶ」というお話,非常に興味深いです。私も同じくトレーニング中に,たくさんのアイディアが浮かびます。古来から哲学者は歩きながら考えるスタイルをとっていたそうですが,感覚的に動いたほうが創造性が促進されることを理解していたのかもしれません。個人的に、こうした身体活動と認知機能との関係には強い関心があり,常々面白いテーマだと感じています。
次に,これまでの活動や作品で特に印象に残っている瞬間やエピソードがあれば教えていただけますでしょうか?
芭蕉と逆転の視点
長谷川さん:芭蕉の〈古池や蛙飛込む水のおと〉の句について、何冊か本を書いてきました。この句はふつう「古池に蛙が飛び込んで水の音がした」と解釈されていますが、「蛙が水に飛び込む音を聞いて、古池のイメージが心に浮かんだ」という句であるということに気づいたとき、目の前がぱっと開ける感じがしました。

こんなナンセンスなことに一生を費やしているのが俳人なのです。ふつうの神経ではなかなかできませんね。
阿久津:長谷川さんがなぜ特別な存在なのかが俳句に素人の私にもなんとなくわかるエピソードに感じました。芭蕉の,私でも知っているあの有名な句に関して長年,専門家の方含めて「そういうもの」として解釈されてきた中で,長谷川さんは何か違和感といいますか言葉にならない「何か」をずっと感じてこられてきた,だからこそ違う解釈の視点を突然得た,そういうことなのかなと想像しました。
はい,これはやはりふつうの神経回路では到達しない境地だと思います。笑
次に,人生においてターニングポイントになったことや,最も苦しかった時期や,それをどう乗り越えたのかというようなことがあれば教えていただけますか?
選択肢は必ず残っている
長谷川さん:いろんなことがありましたが、「人生が苦しい」と思ったことは一度もないのです。理由の一つは自分が巻き込まれるような戦争がなかったことだと思います。その前はそうでなかったし、これからはどうなるかわかりませんが、私たちの世代はたいへん恵まれています。
私は沖縄、広島、長崎を訪ねて戦争の俳句を作っていますが、戦争の悲惨を忘れないために、これはとても大事なことであると思っています。
もう一つの理由は人生についての私自身の考え方によるのではないかと思います。誰だって「大変な事態」は何度か訪れますが、どんな苦境に立っても、選択肢は必ずいくつか残っていて、まったくないということはありません。ないと思うのは、あわてていて選択肢が見えないからではないでしょうか。そんなときこそ落ち着いてどんな選択肢があるか考える。どんな困難でもこれで乗り切れると思っています。
阿久津:長谷川さんのおっしゃるように戦火の中にいる一般の人々を想像すると「自分ごとの苦しいこと」というのはそうでもないと考えることができますね。そしてどんな時でも選択肢は他にもある,それには落ち着くことが大事,というお言葉,勉強になります。物理的に視野を広げる,長い時間軸で考えてみる,そのように俯瞰する習慣作りをしておくと冷静さをかきそうな場面で良い選択ができそうです。
そうした深い人生観のもと,長谷川さんの今後の目標や夢について教えてください。
長谷川さん:対戦相手とか記録とか「姿の見えるもの」と戦いつづけるのがスポーツだと思うのですが、俳句をはじめ文学もまた作品の良し悪しはスポーツの勝ち負け以上にはっきりしています。いい句とそうでない句の違いは厳然としているということです。ただその違いがわかるにはそれなりの精進が必要です。ここはスポーツと似ているかもしれません。
「俳句の仕事」はこれからも1つ1つ地道に取り組んでゆくしかありませんが、私たちが生きている、豊かな世界を喜びも悲しみも含めて俳句で描きたいと思っています。
トレーニングについて一言いうと、私を含め高齢者のトレーニングや体の維持についての研究や実践がもっと進んでほしいと思います。
阿久津:文学作品はスポーツ以上に勝ち負けがはっきりしているということに「そうなのか」と胸を打たれました。高齢者のトレーニングや体の維持についての研究,本当に大事ですね。ウエイトトレーニングと神経新生(脳内で新しい神経細胞が生まれること)や認知機能などの研究は,有酸素運動のそれと比べると蓄積が多くないようですので今後もっと盛んになるといいなと個人的にも思っています。
本日はお忙しい中,本当に有難うございました。最後に、ファンの皆様へメッセージをお願いします。
100年後の未来に向けて
長谷川さん:100年後、今の時代を振り返ったとき、「すばらしい時代だった」といわれるようにしたいというのが私の大きな願いです。お互い、そんな「俳句の仕事」をしたいものですね。