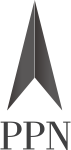「アミロイドβって、生活習慣で減らせるの?」「認知症は遺伝だから予防できないのでは?」
「認知症は遺伝だから…」と諦めていませんか? 実は、2020年に権威ある医学雑誌『The Lancet』が発表した委員会報告によると、”高血圧、運動不足、社会的孤立など12の危険因子を管理することで、認知症の発症リスクの約40%を低減できる可能性がある”と指摘されています。アルツハイマー型認知症の原因物質とされるアミロイドβは、発症の20年以上も前から脳に蓄積し始めますが、この長い潜伏期間こそが、私たちに与えられた「予防のチャンス」なのです。
本記事では、最新の科学的研究に基づいて、アミロイドβの蓄積に影響を与え、脳を守るための7つの生活習慣戦略を詳しく解説します。40代・50代から始める「脳のアンチエイジング」について、エビデンスに基づいた実践的な方法をお届けします。

株式会社ピークパフォーマンスニュートリション(PPN)
代表取締役
パワーリフティングジム TXP代表(公式HP)
NPO法人東京都パワーリフティング協会 副理事長(公式HP)
元パワーリフティング選手(2023年11月の世界選手権を最後に引退)
2010年~2023年105kg級日本代表(2021~2023年団長)
2012~2023年全日本選手権12連覇
NSCA-CPT(2001年取得)
NSCAストレングス&コンディショニングスペシャリスト(2004年取得)
公認スポーツメンタルコーチ


現在プライベートでは東京都立大学大学院人間健康科学研究科において認知運動制御研究の第一人者の樋口貴広教授の元で研究生活を送っている。
アミロイドβとは?認知症の20年前から始まる脳の変化
アミロイドβは、脳内で産生されるタンパク質の断片です。健康な脳でも日々産生されては分解・排出され、バランスが保たれています。しかし、加齢や生活習慣の乱れなど何らかの原因でこのバランスが崩れると、脳内に蓄積して凝集し、「老人斑」と呼ばれるシミのような塊を形成します。この老人斑が、神経細胞の働きを妨げる「神経毒」として作用し、シナプス(神経細胞の接続部)の機能を障害することが分かっています。
一方で、私たちの脳にはBDNF(脳由来神経栄養因子)という、神経細胞の成長を促し、生存を支え、シナプスの働きを強化する重要なタンパク質も存在します。アミロイドβが神経細胞にとっての「毒」であるのに対し、BDNFは「栄養」のような働きをします。つまり、脳の健康を考える上では、アミロイドβの蓄積を抑え、同時にBDNFを増やす生活を送ることが極めて重要なのです。
アミロイドカスケード仮説:認知症への道筋
アルツハイマー型認知症の主要な発症メカニズムとされる「アミロイドカスケード仮説」によれば、病気の進行は以下のような段階を経ると考えられています:
| 段階 | 時期 | 脳の変化 | 症状 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 発症20年前~ | アミロイドβ蓄積開始 | 無症状 |
| 第2段階 | 発症15年前~ | タウタンパク質の蓄積 | 無症状~軽微な物忘れ |
| 第3段階 | 発症10年前~ | 神経細胞の損傷 | 軽度認知障害(MCI) |
| 第4段階 | 発症時 | 広範な脳萎縮 | 認知症症状 |
重要なのは、症状が現れる20年以上前からアミロイドβの蓄積が始まっているという点です。つまり、40~50代の今から対策を始めることで、将来の認知症リスクに影響を与えられる可能性があるのです。

最新研究が明かす:アミロイドβに影響を与える7つの生活習慣
1. 有酸素運動 - 最もエビデンスが豊富な予防法の一つ
運動の脳保護効果
- BDNF(脳由来神経栄養因子)の産生促進
- 脳血流の増加(酸素と栄養の供給アップ)
- アミロイドβ排出システムの活性化への期待
- 海馬体積の維持・増加(記憶中枢の保護)
2023年のSolís-Urra et al.による系統的レビューとメタ分析では、身体能力とアミロイドβの関係について2,619名の参加者を対象に分析が行われました。多くの研究を統合した結果、明確な関連性を見出すには至りませんでしたが、個別の研究では、定期的な身体活動がアミロイドβの蓄積を抑制する可能性が示唆されています。何よりも、運動がBDNFを増やし、脳の神経ネットワークを強化することは数多くの研究で支持されています。
推奨される運動プログラム:
- ・週150分以上の中強度有酸素運動(早歩き、水泳、サイクリング)
- ・週2回以上の筋力トレーニング
- ・毎日8,000~10,000歩のウォーキング
- ・運動強度:最大心拍数の60~75%(会話がやや弾む程度)
2. 質の高い睡眠 - 脳のクリーニングタイム
睡眠中の脳内浄化システム
- グリンファティック系の活性化
- 睡眠中に脳の老廃物排出が活発化
- 深い睡眠(徐波睡眠)が特に重要
- 7-8時間の睡眠が最適と報告
睡眠不足は、脳内のアミロイドβ蓄積と関連することがワシントン大学などの研究で示唆されています。特に深い睡眠(ノンレム睡眠)の時に、脳の老廃物排出システムである「グリンファティック系」が最も活発に働き、アミロイドβなどが効率的に洗い流されると考えられています。
良質な睡眠のための習慣例:
| 時間帯 | 推奨行動 | 理由 |
|---|---|---|
| 起床時 | 朝日を15分浴びる | 体内時計のリセット |
| 午後2時以降 | カフェイン摂取を控える | 覚醒作用が夜まで残る可能性 |
| 就寝2時間前 | スマホ・PCを避ける | ブルーライトが睡眠ホルモンを抑制 |
| 就寝前 | 室温を快適な温度に調整 | 深部体温の自然な低下を促進 |
3. 地中海式食事法 - 脳を守る食事パターン
地中海式食事法の特徴
- オリーブオイルを主要な脂質源に
- 魚介類を週2回以上
- 野菜・果物を豊富に
- 全粒穀物、ナッツ類、豆類を積極的に
- 赤肉や加工肉の摂取を控えめに
地中海式食事法を遵守している人は、そうでない人と比較して脳内のアミロイドβ蓄積が少ない傾向にあることが、複数の観察研究で報告されています。特に、オメガ3脂肪酸(DHA・EPA)が豊富な魚の摂取は重要で、ある観察研究では、週に1回以上魚を食べる人は、ほとんど食べない人に比べて加齢に伴う認知機能の低下が緩やかだったと報告されています。
脳の健康をサポートする食材例:
- 青魚(サバ、イワシ、サンマ)- DHA・EPA豊富
- ベリー類(ブルーベリーなど) - アントシアニンによる抗酸化作用
- ウコン - クルクミンの抗炎症作用
- 緑茶 - カテキン・L-テアニンの神経保護作用
- 緑黄色野菜(ブロッコリーなど) - ビタミンK、葉酸が豊富
- くるみ - αリノレン酸、ポリフェノール
- カカオ(ダークチョコレート) - フラボノイドによる血流改善
- アボカド - 一価不飽和脂肪酸が豊富
- エクストラバージンオリーブオイル - オレオカンタールがアミロイドβ除去を促進する可能性
- 卵 - コリン(アセチルコリンの原料)が豊富
4. 社会的交流 - 脳を活性化する良質な刺激
孤独は喫煙と同程度に健康リスクを高めることが知られています。社会的な孤立は、認知症リスクを高める要因の一つであることが、大規模な研究で報告されています。
脳を活性化する社会活動の例:
- ・週1回以上の友人との会食や趣味活動
- ・ボランティア活動への参加
- ・地域のサークルや習い事への参加
- ・多世代交流(孫との触れ合いなど)
- ・オンラインでも良いので定期的な交流を持つ

5. 知的活動 - 認知予備能を高める
「認知予備能(Cognitive Reserve)」とは、脳に病理的な変化が生じても、認知機能を維持する能力のことです。教育年数が長い人や、生涯にわたって知的好奇心を持ち学習を続けている人は、同じ程度のアミロイドβが蓄積していても、症状が出にくいことが分かっています。
推奨される知的活動(観察研究より):
| 活動 | 関連する報告例 | 推奨頻度 |
|---|---|---|
| 新しい言語の学習 | 認知症リスク低下と関連 | 週数回 |
| 楽器演奏 | 認知機能低下リスク低下と関連 | 週数回 |
| 読書 | 認知症リスク低下と関連 | 毎日30分 |
| ボードゲーム・パズル | 記憶力低下リスク低下と関連 | 週数回 |
6. ストレス管理 - 慢性ストレスは脳の敵
慢性ストレスが脳に与える影響:
・コルチゾールによる海馬の機能低下
・アミロイドβ産生促進の可能性
・脳内の炎症促進
・血糖値上昇による脳へのダメージ
慢性的なストレスは、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を増加させ、記憶中枢である海馬の神経新生を抑制し、機能を低下させることが知られています。また、アミロイドβの産生を促進する可能性も指摘されています。
科学的に実証されたストレス軽減法:
- ・マインドフルネス瞑想:脳構造の変化と関連する報告あり
- ・ヨガ:コルチゾールレベルの低下と関連
- ・太極拳:認知機能スコアの改善報告あり
- ・深呼吸法:4-7-8呼吸法(4秒吸う、7秒止める、8秒吐く)など
- ・自然の中での散歩(森林浴):ストレスホルモンの減少
7. 血管リスク因子の管理 - 脳血管を守る
「脳に良いことは心臓にも良い」という言葉通り、血管の健康は脳の健康に直結します。中年期の高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満といった血管リスク因子は、アミロイドβの蓄積を促進する可能性があり、脳血管性認知症のリスクも高めます。
管理すべき数値目標(一般的な目安):
| 項目 | 目標値 | 対策 |
|---|---|---|
| 血圧 | 130/80 mmHg未満 | 減塩、運動、体重管理 |
| HbA1c | 6.0%未満 | 糖質管理、運動療法 |
| LDLコレステロール | 120 mg/dL未満 | 飽和脂肪酸制限、食物繊維 |
| BMI | 18.5-24.9 | カロリー管理、運動 |
最新の診断技術:アミロイドPETで早期発見が可能に
近年、脳内のアミロイドβ蓄積を画像で可視化する「アミロイドPET検査」が臨床応用されています。2018年のShea et al.によるメタ分析では、アミロイドPET検査により、専門医の診断が約35%の患者で変更され、約60%で治療方針が変更されたことが報告されており、診断精度向上への貢献が示されています。
また、2024年のAbanto et al.によるメタ分析では、新しい治療薬である抗アミロイドβ抗体薬が、脳内のアミロイドβを除去するだけでなく、脳脊髄液中のアミロイドβ42濃度を正常化させ、認知機能の低下を遅らせることと関連している可能性が示されました。これらの技術の進歩により、早期診断・早期介入の重要性がますます高まっています。
40代から始める「脳活」プログラム:実践例
週間スケジュール例
| 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|---|
| 月 | ウォーキング30分 | 地中海式ランチ | 読書30分 |
| 火 | ヨガ20分 | 友人とランチ | 語学学習30分 |
| 水 | 筋トレ20分 | 魚料理 | 瞑想10分 |
| 木 | ウォーキング30分 | サラダランチ | パズル・数独 |
| 金 | ストレッチ15分 | 地中海式ランチ | 音楽鑑賞 |
| 土 | サイクリング45分 | 家族と外食 | 趣味活動 |
| 日 | 自然散策60分 | 料理を楽しむ | 日記を書く |

よくある誤解と注意点
誤解1:「遺伝だから予防できない」
APOE4という遺伝子型を持つ人はアルツハイマー病のリスクが高いことが知られています。しかし、これは「運命」ではありません。APOE4を持っていても、健康的な生活習慣(運動、食事、禁煙など)を実践することで、リスクが低い生活習慣の人と同程度まで発症リスクを低減できる可能性を示唆する研究があります。遺伝はあくまでリスク因子の一つであり、生活習慣の力はそれを上回る可能性があるのです。
誤解2:「高齢になってからでは遅い」
もちろん早く始めるに越したことはありませんが、何歳からでも遅すぎるということはありません。80歳から運動を始めたグループでも、認知機能の改善が見られたという研究報告もあります。脳は生涯を通じて変化する「可塑性」を持っています。
誤解3:「サプリメントだけで予防できる」
特定のサプリメントを飲むだけで認知症を予防できるという確固たる証拠は、現時点ではありません。本記事で解説した総合的な生活習慣の改善こそが、最も強力で信頼性の高い予防戦略です。サプリメントは、あくまでこの土台の上で、食事だけでは不足しがちな特定の栄養素を補うための「補助的」な選択肢と考えるべきです。
まとめ:今日から始める脳の健康習慣
アミロイドβの蓄積は、認知症発症のかなり前から静かに始まります。しかし、その長い潜伏期間は、私たちにとって予防のための貴重な時間です。生活習慣の改善により、その蓄積プロセスに良い影響を与え、将来のリスクを低減できる可能性があります。
重要なのは、どれか一つの方法に頼るのではなく、複数のアプローチを組み合わせることです。運動、睡眠、食事、社会活動、知的活動、ストレス管理、血管リスク管理——これらすべてが相乗効果を生み出し、脳の健康を守るための強力な盾となり得ます。
今すぐ始められる3つのアクション:
- 毎日プラス10分の早歩きから習慣にする
- 睡眠時間を7時間以上確保することを意識する
- 週に2回は青魚を食卓に取り入れる
40代・50代の「今」こそが、将来の脳の健康を左右する重要な時期です。小さな習慣の積み重ねが、20年後、30年後のあなた自身を支える基盤となります。今日から、あなたの脳を守る生活を始めてみませんか?
生活習慣という土台を固めた上で:科学的根拠に基づく栄養サポートという選択肢

脳の健康維持を多角的にサポート
本記事で解説した7つの生活習慣が、脳の健康を守るための最も重要な土台です。その上で、食事だけでは補いきれない栄養素を効率的に摂取したいと考える方のために、科学的知見に基づいた栄養サポートという選択肢があります。111'NEURO DRIVEは、脳の健康維持に関連する9種類の成分を配合したサプリメントです。
脳の健康をサポートする主要成分
DHA・EPA(オメガ3脂肪酸)/ LIPAMIN PS™(ホスファチジルセリン)/ ホワイトクルクミノイド®(高吸収クルクミン)/ α-GPC(コリン補給)など、研究で注目される9種類の成分を配合。
✓ BSCGドーピング検査認証取得(全ロット検査済み)
✓ 40代からの脳の健康維持をサポート
✓ 生活習慣改善との相乗効果を期待
✓ 医薬品レベルの品質管理で安心
本記事の内容は、科学的研究に基づく情報提供を目的としており、特定の製品の効果を保証したり、医学的アドバイスに代わるものではありません。認知機能に不安がある場合や、現在治療中の疾患がある場合は、必ず専門の医師にご相談ください。生活習慣の改善は予防的効果が期待できますが、その効果には個人差があります。
参考文献
Livingston, G., et al. (2020). Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. The Lancet, 396(10248), 413-446.
Abanto, J., et al. (2024). Increases in amyloid-β42 slow cognitive and clinical decline in Alzheimer's disease trials. Brain, awae216.
Shea, Y. F., et al. (2018). Impact of Amyloid PET Imaging in the Memory Clinic: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Alzheimer's Disease, 66(1), 323-335.
Solís-Urra, P., et al. (2023). Physical Performance and Amyloid-β in Humans: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Journal of Alzheimer's Disease, 96(4), 1631-1652.
de Wilde, A., et al. (2018). Disclosure of amyloid positron emission tomography results to individuals without dementia: a systematic review. Alzheimer's Research & Therapy, 10(1), 72.
Agah, E., et al. (2018). CSF and blood biomarkers in amyotrophic lateral sclerosis: protocol for a systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews, 7(1), 237.
Filippi, M., et al. (2022). Amyloid-Related Imaging Abnormalities and β-Amyloid–Targeting Antibodies: A Systematic Review. JAMA Neurology, 79(3), 291-304.