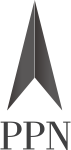「人の名前がすぐに出てこない」「集中力が続かない」——こうした悩みを感じる方は少なくありません。
そんな中、「脳に良い」とされて人気のサプリメント成分がイチョウ葉エキスです。ヨーロッパでは医薬品として使われ、日本でも機能性表示食品として多くの製品が販売されています。
しかし「効く」「効かない」と様々な情報があり、何を信じれば良いのか迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、最新の査読済み論文を基にイチョウ葉エキスの認知機能への影響を解説します。専門的な内容も多いですが、興味のある方はぜひ最後までお付き合いください。

株式会社ピークパフォーマンスニュートリション(PPN)
代表取締役
パワーリフティングジム TXP代表(公式HP)
NPO法人東京都パワーリフティング協会 副理事長(公式HP)
元パワーリフティング選手(2023年11月の世界選手権を最後に引退)
2010年〜2023年105kg級日本代表(2021〜2023年団長)
2012〜2023年全日本選手権12連覇
NSCA-CPT(2001年取得)
NSCAストレングス&コンディショニングスペシャリスト(2004年取得)
公認スポーツメンタルコーチ


現在プライベートでは東京都立大学大学院人間健康科学研究科において認知運動制御研究の第一人者である樋口貴広教授の元で研究生活を送っている。
イチョウ葉エキスとは?有効成分と品質基準を理解する
イチョウ葉エキスは、イチョウの葉から抽出された成分です。ヨーロッパでは医薬品として認知機能障害や末梢循環障害の治療に用いられています(Herrschaft et al., 2012)。
効果の源となる主な有効成分は以下の2種類です:
- フラボノイド配糖体(22〜27%):強力な抗酸化作用を持ち、脳を酸化ストレスから守ります(Morató et al., 2023)。
- テルペンラクトン(5〜7%):血液循環を改善し、脳への酸素と栄養の供給を促進します(Tan et al., 2014)。
品質の見極め方
医薬品グレードの製品(EGb 761®など)では、アレルゲン物質であるギンコ酸を5ppm以下に厳格に管理しています。これが品質の重要な指標となります(Hashiguchi et al., 2015)。
イチョウ葉エキスが脳に働きかける4つのメカニズム
イチョウ葉エキスは単一の作用ではなく、複数のメカニズムを通じて脳機能に影響を与えます(Yuan et al., 2017)。
メカニズム1:脳血流と微小循環の改善
イチョウ葉エキスの最も確立された効果が、脳血流の改善です。Li et al. (2017)の研究では、脳卒中患者で脳血流の有意な増加が確認されました。
このメカニズムには3つの経路があります:
- 血管の拡張:一酸化窒素(NO)の産生を促し、血管を広げます。
- 血液の流動性向上:血小板の凝集を抑え、血液をサラサラにします(Tan et al., 2014)。
- 微小血管での酸素供給:赤血球の柔軟性を高め、毛細血管での酸素供給を最適化します。
脳は体重の約2%ですが、全身の酸素消費量の約20%を占めます。記憶や判断を司る部位は、特に血流変化に敏感です。
メカニズム2:抗酸化作用による脳の保護
Morató et al. (2023)の研究では、軽度認知障害(MCI)患者にイチョウ葉エキスを6ヶ月間投与したところ、炎症マーカーと酸化ストレスマーカーが改善しました。
この抗酸化作用は4つの経路で発揮されます:
- 活性酸素の除去:細胞を傷つける活性酸素を直接捕捉します。
- 抗酸化酵素の活性化:体内の抗酸化システムを強化します。
- 金属イオンの無害化:酸化を促進する金属イオンを結合して無害化します。
- エネルギー産生の保護:細胞のエネルギー工場であるミトコンドリアを守ります。
加齢に伴う認知機能低下の主要な原因の一つが、この酸化損傷の蓄積です(Zhang et al., 2016)。
メカニズム3:神経伝達物質系の調節
イチョウ葉エキスは、複数の神経伝達物質に作用することが明らかになっています(Weinmann et al., 2010):
-
アセチルコリン系:アセチルコリンエステラーゼ(
アセチルコリンを分解する酵素)の活性を緩やかに抑制し、記憶・学習に重要なアセチルコリンの濃度を維持します。 - モノアミン系:ドーパミン、ノルアドレナリン、セロトニンの代謝に影響し、注意力や気分の調節に寄与します。
- グルタミン酸系:過剰なグルタミン酸による神経細胞のダメージを防ぎつつ、正常な学習機能は維持します。
メカニズム4:神経の成長と炎症の抑制
イチョウ葉エキスは、神経細胞の成長を促す因子(BDNF)を増やす可能性が動物実験で示されています(Tan et al., 2014)。また、Morató et al. (2023)の研究では、脳の炎症を示すマーカーが低下しました。慢性的な炎症はアルツハイマー病などに関わるため、その抑制は重要です。
複合的作用の重要性
これら4つのメカニズムは相互に関連しながら、脳の健康を多角的に支えます。この多元的な作用こそがイチョウ葉エキスの特徴です(Yuan et al., 2017)。
エビデンスの全体像:なぜ研究結果は一致しないのか
イチョウ葉エキスの認知機能への効果については、研究によって結論が異なります。この「不一致」には、科学的に理解可能な理由があります。最新のメタアナリシスとシステマティックレビューから、その全体像を解き明かします。
肯定的エビデンス:軽度認知障害と認知症における効果
Riepe et al. (2025)の最新メタアナリシスでは、軽度認知症患者において、EGb 761®(1日240mg)の有意な認知機能改善効果が確認されています。
Tan et al. (2014)のメタアナリシス(2,561名のデータ)では、認知機能障害および認知症患者において、以下の評価で有意な改善が報告されています:
- ADAS-Cog:認知機能の包括的評価
- MMSE:全般的認知機能
- ADL:日常生活動作能力
Li et al. (2017)の脳卒中患者を対象とした研究では、すべての評価項目で有意な改善が認められました。血管性要因による認知機能低下に対して、特に有効である可能性を示しています。
否定的・限定的エビデンス:健常高齢者における予防効果
一方で、Snitz et al. (2009)のGEM study(Ginkgo Evaluation of Memory study)は、75歳以上の健常高齢者約3,000名を平均6.1年間追跡しました。この研究では、イチョウ葉エキス(1日240mg)投与群とプラセボ群の間で、認知症発症率に有意差は認められませんでした。
この結果については、研究デザイン上の特性を考慮する必要があります:
- 対象者の特性:健康意識が高く、ベースラインの認知機能も高い集団であった可能性。
- 介入開始時期:認知症の変化は症状出現の20〜30年前から始まります。75歳からの介入では既に進行している可能性。
- 評価方法:「認知症発症」という二値的な評価では、「低下速度の緩和」といった効果を捉えきれない可能性。
研究ごとのバラつきを生む主な要因
Yuan et al. (2017)のレビューでは、研究ごとのバラつきの主要な原因として以下が指摘されています:
- 対象集団の違い:健常者、軽度認知障害、認知症では反応性が異なる。
- 製剤の品質:標準化された製剤とそうでない製剤では効果が異なる可能性。
- 用量と投与期間:1日80mg〜600mg、6週間から6年以上まで多様。
- 評価方法の違い:使用される評価尺度が研究により異なる。
最新のエビデンス統合:2025年の知見
Riepe et al. (2025)の最新メタアナリシスでは、軽度認知症患者において、EGb 761® 240mg/日の投与が認知機能、日常生活動作、神経精神症状のすべてで有意な改善をもたらすことが示されています。
Wang et al. (2025)のネットワークメタアナリシスでは、イチョウ葉エキスが健常成人においても認知機能改善効果を持つことが示唆されています。ただし効果サイズは小さく、臨床的意義については議論の余地があります。
用量と投与期間:科学的根拠に基づく推奨
エビデンスに基づく最適な用量と投与期間について、対象集団別に整理します。
| 対象集団 | 推奨用量(標準化エキス) | 投与期間 | 期待される効果 | 主要エビデンス |
|---|---|---|---|---|
| 軽度〜中等度認知症 | 240mg/日(EGb 761®相当) フラボノイド配糖体 52.8〜64.8mg テルペンラクトン 12〜16.8mg |
22〜52週 | ADAS-Cog、MMSE、ADLでの有意な改善 |
Riepe et al., 2025 Herrschaft et al., 2012 |
| 軽度認知障害(MCI) | 240mg/日 | 24週以上 | 特定の認知ドメインでの改善、炎症マーカーの低下 |
Morató et al., 2023 Tan et al., 2014 |
| 虚血性脳卒中後 | 150〜240mg/日 | 12〜24週 | 認知機能、神経機能、ADLの改善 |
Li et al., 2017 Cui et al., 2023 |
| 健常中高年(記憶力維持) | 80〜240mg/日 フラボノイド配糖体 19.2mg以上 テルペンラクトン 4.88mg以上 |
12〜24週 | 特定の記憶タスクでの維持・改善 |
Kaschel, 2011 Santos et al., 2003 |
用量設定の科学的根拠
上記の用量は、臨床試験で有効性が実証された標準化イチョウ葉エキス(特にEGb 761®)に基づいています。1日あたりフラボノイド配糖体19.2mg以上、テルペンラクトン4.88mg以上(エキス換算で80mg以上)を目安とする研究が多く見られます。
安全性と医薬品相互作用
Tan et al. (2014)のメタアナリシスでは、2,561名のデータから安全性が評価されています。全体として、イチョウ葉エキスは良好な忍容性を示しています。
報告されている有害事象
臨床試験で報告された有害事象は、多くが軽度で一過性です(Hashiguchi et al., 2015):
- 消化器症状(胃腸不快感、吐き気):発現率2〜5%。多くは自然に改善します。
- 頭痛:発現率1〜3%。軽度で一時的です。
- 皮膚反応(発疹、かゆみ):発現率1%未満。
これらの発現率はプラセボ群と有意差がない場合が多く、重篤な副作用の報告は非常に少ないことが確認されています。標準化された製剤を適切な用量で使用する限り、安全性は良好と考えられます。
医薬品相互作用:科学的根拠の整理
イチョウ葉エキスと医薬品の相互作用については、理論的な懸念と実際の臨床的意義を区別することが重要です。
医薬品を服用中の方は医師・薬剤師に相談を
抗凝固薬・抗血小板薬との併用
イチョウ葉エキスには血小板凝集を抑える作用があるため、理論的には抗凝固薬や抗血小板薬との併用で出血リスクが増加する可能性が指摘されています。ただし、メタアナリシスでは出血関連有害事象に有意差は認められていません(Tan et al., 2014; Hashiguchi et al., 2015)。
念のため、抗凝固療法中の方は医師に相談してください。手術予定がある場合は、術前2週間程度の中止が提案されることがあります。
効果の個人差を生む要因
同じイチョウ葉エキスを摂取しても、効果を実感する人としない人がいます。主な要因は以下の通りです:
- 認知機能の状態:既に認知機能低下が始まっている方では効果が検出されやすい傾向があります(Riepe et al., 2025)。健常で認知機能が高い方では、改善の余地が小さく効果を実感しにくい可能性があります。
- 血管性リスク因子:高血圧、糖尿病、脳血管障害の既往などがある方では、血流改善作用がより顕著に現れる可能性があります(Li et al., 2017)。
- 生活習慣:運動、食事、睡眠などの生活習慣が脳の健康状態を左右します。これらが最適化されている方では、サプリメントの上乗せ効果は相対的に小さくなります。
まとめ:イチョウ葉エキスの科学的位置づけと賢い活用法
複数の査読済み論文を精査した結果、以下のコンセンサスが得られます:
- イチョウ葉エキス(特にEGb 761®のような標準化製剤)は、軽度認知障害や軽度〜中等度認知症患者において、認知機能、日常生活動作、神経精神症状の改善に一定の効果を持つことが確認されています(Riepe et al., 2025; Tan et al., 2014)。
- 健常高齢者における認知症予防効果は、大規模研究で確認されていません(Snitz et al., 2009)。ただし、特定の記憶タスクでの改善効果は示唆されています(Kaschel, 2011)。
- 虚血性脳卒中後の認知機能回復においては、有望なエビデンスがあります(Li et al., 2017; Cui et al., 2023)。
- 安全性は概ね良好ですが、医薬品との相互作用については医師・薬剤師への相談をお勧めします(Hashiguchi et al., 2015)。
私がパワーリフティング選手として学んだ最も重要な教訓は、「ピークパフォーマンスは総合力で決まる」ということです。トップアスリートは、トレーニング、栄養、回復、メンタル、すべてを最適化します。サプリメントは、その上に載せる最後のピースです。
認知機能も同じです。週150分程度の運動、バランスの取れた食事、質の高い睡眠、充実した社会的つながり——これらが最も強固なエビデンスを持つ認知機能維持策です。イチョウ葉エキスは、これらの基本を押さえた上で、さらなるサポートを求める方にとって、検討する価値のある選択肢の一つです。
複数成分を組み合わせた多角的アプローチ:111'NEURO DRIVE

単一成分に頼るのではなく、複数の有効成分を組み合わせることで、脳機能を多角的にサポートするという考え方があります。PPNが開発した111'NEURO DRIVEは、この考えを形にした製品です。
9種類の認知機能サポート成分
イチョウ葉エキス、DHA・EPA、α-GPC、LIPAMIN PS™、Neumentix®、ホワイトクルクミノイド®、Suntheanin®、Zynamite®、ムクナ抽出物を配合。脳血流改善、抗酸化作用、神経伝達物質の最適化、神経可塑性の向上、抗炎症作用など、複数のメカニズムから脳のパフォーマンスをサポートします。
✓ 全ロットでBSCGドーピング検査認証を取得済み
✓ 各成分の含有量を公開
✓ アスリートから経営者、受験生まで幅広く愛用
参考文献
- Riepe, M., Hoerr, R., & Schlaefke, S. (2025). Ginkgo biloba extract EGb 761 is safe and effective in the treatment of mild dementia – a meta-analysis of patient subgroups in randomised controlled trials. The World Journal of Biological Psychiatry, 26, 119-129. https://doi.org/10.1080/15622975.2024.2446830
- Wang, Z.-Y., Deng, Y.-L., Zhou, T.-Y., Liu, Y., & Cao, Y. (2025). Effects of natural extracts in cognitive function of healthy adults: a systematic review and network meta-analysis. Frontiers in Pharmacology, 16, 1573034. https://doi.org/10.3389/fphar.2025.1573034
- Morató, X., Marquié, M., Tartari, J. P., et al. (2023). A randomized, open-label clinical trial in mild cognitive impairment with EGb 761 examining blood markers of inflammation and oxidative stress. Scientific Reports, 13, 5305. https://doi.org/10.1038/s41598-023-32515-6
- Cui, M., You, T., Zhao, Y., et al. (2023). Ginkgo biloba extract EGb 761® improves cognition and overall condition after ischemic stroke: Results from a pilot randomized trial. Frontiers in Pharmacology, 14, 1147860. https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1147860
- Li, S., Zhang, X., Fang, Q., et al. (2017). Ginkgo biloba extract improved cognitive and neurological functions of acute ischaemic stroke: a randomised controlled trial. Stroke and Vascular Neurology, 2(4), 189-197. https://doi.org/10.1136/svn-2017-000104
- Yuan, Q., Wang, C.-W., Shi, J., & Lin, Z.-X. (2017). Effects of Ginkgo biloba on dementia: An overview of systematic reviews. Journal of Ethnopharmacology, 195, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.jep.2016.12.005
- Zhang, H.-F., Huang, L.-B., Zhong, Y.-B., et al. (2016). An Overview of Systematic Reviews of Ginkgo biloba Extracts for Mild Cognitive Impairment and Dementia. Frontiers in Aging Neuroscience, 8, 276. https://doi.org/10.3389/fnagi.2016.00276
- Hashiguchi, M., Ohta, Y., Shimizu, M., Maruyama, J., & Mochizuki, M. (2015). Meta-analysis of the efficacy and safety of Ginkgo biloba extract for the treatment of dementia. Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences, 1, 14. https://doi.org/10.1186/s40780-015-0014-7
- Tan, M.-S., Yu, J.-T., Tan, C.-C., et al. (2014). Efficacy and Adverse Effects of Ginkgo Biloba for Cognitive Impairment and Dementia: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Alzheimer's Disease, 43(2), 589-603. https://doi.org/10.3233/JAD-140837
- Herrschaft, H., Nacu, A., Likhachev, S., Sholomov, I., Hoerr, R., & Schlaefke, S. (2012). Ginkgo biloba extract EGb 761® in dementia with neuropsychiatric features: a randomised, placebo-controlled trial to confirm the efficacy and safety of a daily dose of 240 mg. Journal of Psychiatric Research, 46(6), 716-723. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2012.03.003
- Ihl, R., Tribanek, M., & Bachinskaya, N. (2011). Efficacy and Tolerability of a Once Daily Formulation of Ginkgo biloba Extract EGb 761® in Alzheimer's Disease and Vascular Dementia: Results from a Randomised Controlled Trial. Pharmacopsychiatry, 45(02), 41-46. https://doi.org/10.1055/s-0031-1291217
- Weinmann, S., Roll, S., Schwarzbach, C., Vauth, C., & Willich, S. N. (2010). Effects of Ginkgo biloba in dementia: systematic review and meta-analysis. BMC Geriatrics, 10, 14. https://doi.org/10.1186/1471-2318-10-14
- Wang, B.-S., Wang, H., Song, Y.-Y., et al. (2010). Effectiveness of standardized ginkgo biloba extract on cognitive symptoms of dementia with a six-month treatment: a bivariate random effect meta-analysis. Pharmacopsychiatry, 43(3), 86-91. https://doi.org/10.1055/s-0029-1242817
- Snitz, B. E., O'Meara, E. S., Carlson, M. C., et al. (2009). Ginkgo biloba for preventing cognitive decline in older adults: a randomized trial. JAMA, 302(24), 2663-2670. https://doi.org/10.1001/jama.2009.1913
- Kaschel, R. (2011). Specific memory effects of Ginkgo biloba extract EGb 761 in middle-aged healthy volunteers. Phytomedicine, 18(14), 1202-1207. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2011.06.021
- Santos, R. F., Galduróz, J. C. F., Barbieri, A., Castiglioni, M. L. V., Ytaya, L. Y., & Bueno, O. F. A. (2003). Cognitive performance, SPECT, and blood viscosity in elderly non-demented people using Ginkgo biloba. Pharmacopsychiatry, 36(03), 127-133. https://doi.org/10.1055/s-2003-41197
本記事の内容は、科学的根拠に基づく情報提供を目的としており、医学的アドバイスを代替するものではありません。特定の健康状態や疾患の治療、サプリメントの摂取については、必ず医療専門家(医師・薬剤師)にご相談ください。特に医薬品を服用中の方は、自己判断での摂取を避け、必ず医療機関にご相談ください。