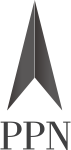「集中力が続かない」「記憶力が気になる」「仕事や勉強の効率を上げたい」──そんな悩みを抱えていませんか?
近年、認知機能をサポートするサプリメントが注目を集めています。しかし、市場には数多くの製品があり、「どの成分が本当に効果的なのか」「科学的根拠はあるのか」と迷う方も多いでしょう。
本記事では、科学的研究に基づいて効果が実証されている認知機能サポート成分を紹介し、その特徴や作用機序、臨床試験データを詳しく解説します。査読済み研究論文を精査し、信頼性の高い情報のみをお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。

代表取締役 阿久津貴史 (公式HP)
元パワーリフティング選手(2023年11月の世界選手権を最後に引退)
2010年~2023年105kg級日本代表(2021~2023年団長)
2012~2023年全日本選手権12連覇
パワーリフティングジム TXP代表
NSCA-CPT(2001年取得)
NSCAストレングス&コンディショニングスペシャリスト(2004年取得)
公認スポーツメンタルコーチ


現在プライベートでは東京都立大学大学院人間健康科学研究科において認知運動制御研究の第一人者の樋口貴広教授の元で研究生活を送っている。
認知機能サプリメントとは?なぜ今注目されているのか
認知機能サプリメントとは、脳の働きをサポートし、記憶力、集中力、学習能力、判断力などの認知機能を向上させることを目的としたサプリメントです。欧米では「ヌートロピック(Nootropics)」とも呼ばれ、脳のパフォーマンスを高める物質の総称として使われています。
市場規模の急成長が示す需要の高まり
脳関連のサプリメント世界市場は、2024年に113億米ドルに達し、2034年までに約321億米ドルに達すると予想されています。2024年から2033年にかけて11%のCAGR(年平均成長率)で拡大すると予測されており、その成長率は驚異的です。
この急成長の背景には、以下のような要因があります:
- ・高齢化社会の進展:認知症予防への関心の高まり
- ・デジタル社会のストレス:情報過多による集中力低下への対策
- ・パフォーマンス向上への意識:アスリート、ビジネスパーソン、学生の競争力強化
- ・最新研究の進展:エビデンスに基づく成分の増加
市場がこれだけ急成長しているからこそ、玉石混交の情報の中から「本当に科学的根拠のある成分はどれなのか」を正しく見極める必要があります。では、実際にどのような成分がその有効性を証明されているのでしょうか。
認知機能をサポートする主要成分一覧

ではここから、信頼できる研究によって認知機能向上効果が実証されている主要成分を紹介します。各成分の特徴、作用機序、臨床試験データを詳しく解説していきます。
1. Neumentix®(スペアミント抽出物)- 持続的な集中力向上
主な効果
- 持続的注意力:90日間で約11%向上
- 作業記憶の質:15%向上
- 空間作業記憶の正確性:9%向上
Neumentix®は、特別に育種されたスペアミント(Mentha spicata L.)から抽出されたフェノール複合体です。通常のスペアミントよりもロスマリン酸を高含有し、50種類以上のフェノール化合物を含んでいます。
作用機序:
- 酸化ストレスの低下
- アセチルコリンの増加(学習と記憶の神経伝達物質)
- 神経細胞の新生促進
- 神経保護作用による脳内ニューロンの健康維持
臨床試験データ:
健康な若年成人142名(平均年齢27歳)を対象とした90日間の二重盲検プラセボ対照試験では、Neumentix® 900mg/日の摂取により、持続的注意力がベースラインから11%向上しました(Falcone et al., 2019)。
高齢者(50-70歳)を対象とした試験でも、作業記憶の質15%向上、空間作業記憶の正確性9%向上が確認されています(Herrlinger et al., 2018)。
2. α-GPC(アルファ-グリセロホスホコリン)- 脳内アセチルコリンの最適化
主な効果
- アセチルコリン前駆体として最も効率的
- 学習能力・記憶力の向上
- 認知症患者の認知機能改善
α-GPCは、大豆レシチンから得られるコリン化合物で、血液脳関門を通過し、脳内でアセチルコリンに変換される最も効率的な前駆体です。
アセチルコリンの重要性:
アセチルコリンは、記憶・学習・注意力に深く関わる神経伝達物質です。その不足は認知障害の主要な原因の一つとされています。α-GPCは、このアセチルコリンの原料を効率的に脳に供給します。
研究エビデンス:
2023年に発表されたシステマティックレビューとメタ分析(Sagaro et al.)では、α-GPC単独または他の成分との組み合わせにより、認知機能テスト(MMSE、ADAS-Cog)での有意な改善が報告されています。
3. ホスファチジルセリン(PS)- 脳細胞膜の健康維持
主な効果
- 記憶機能の改善(特に遅延言語記憶)
- 実行機能・精神的柔軟性の向上
- ストレスホルモン(コルチゾール)の抑制
ホスファチジルセリン(PS)は、脳細胞膜の主要構成成分です。加齢とともに減少するPSを補給することで、神経細胞の機能を正常化し、認知機能を改善します。
作用機序:
- 細胞膜の流動性と組成の復旧
- 酵素活性の回復(プロテインキナーゼC、Na+/K+-ATPアーゼなど)
- 神経伝達物質の合成と放出促進
- 樹状突起棘密度の維持(記憶の物理的基盤)
臨床試験データ:
日本人高齢者78名を対象とした6ヶ月間の二重盲検プラセボ対照試験では、大豆由来PS(100mg、300mg/日)の投与により、記憶スコアが有意に改善されました(Kato-Kataoka et al., 2010)。
2022年のメタ分析では、9件の研究(961名)を対象に分析した結果、PSが認知機能低下のある高齢者の記憶に対して正の効果があると結論づけられました。
4. L-テアニン(Suntheanin®)- リラックスした集中状態
主な効果
- α波の増加(リラックスした覚醒状態)
- ストレスホルモン(コルチゾール)の抑制
- 睡眠の質の向上
- 不安感の軽減
L-テアニンは、緑茶に含まれるアミノ酸の一種で、血液脳関門を通過してGABA受容体に作用し、リラックス効果を発揮します。
脳波測定による科学的エビデンス:
L-テアニン摂取後30-60分でα波活動が顕著に増加することが確認されています。α波は、リラックスしながらも覚醒している理想的な集中状態を示す脳波です。
臨床試験データ:
2019年の研究では、健康な成人30名に対して4週間、1日200mgのL-テアニンを摂取させた結果、気分の落ち込み、不安感、睡眠の質が有意に改善されました(Hidese et al., 2019)。
ADHD男子98名を対象とした6週間の試験では、1日400mgのL-テアニン摂取により、睡眠効率の向上、睡眠時間の増加が客観的に測定されました(Alternative Therapies in Health and Medicine, 2011)。
5. Zynamite®(マンゴー葉エキス)- カフェインを超える持続的覚醒
主な効果
- 反応時間9.9%短縮
- 精神的疲労40%軽減
- 注意力の正確性向上
- 副作用なし(血圧・心拍数への影響なし)
Zynamite®は、マンゴー(Mangifera indica)の葉から抽出された特許取得済みのエキスで、マンギフェリンを60%以上含有するよう規格化されています。
カフェインとの違い:
カフェインのような一時的な覚醒作用ではなく、持続的で安定した集中力をサポートします。重要なのは、血圧や心拍数への影響がなく、効果減退後の疲労感(クラッシュ)もないことです。
| 項目 | カフェイン | Zynamite® |
|---|---|---|
| 血圧・心拍数への影響 | 上昇 | 影響なし |
| 効果の持続性 | 短時間(約4時間) | 長時間(約8時間) |
| 効果減退後の疲労感 | あり | なし |
| 依存性 | あり | なし |
臨床試験データ:
健康な成人70名を対象とした二重盲検プラセボ対照クロスオーバー試験では、Zynamite 300mgの単回摂取により、注意力の精度、エピソード記憶、認知負荷バッテリーで有意な改善が認められました(Wightman et al., 2020)。
6. その他の重要な認知機能サポート成分

イチョウ葉エキス - 脳血流の改善
イチョウ葉エキスは、13種類のフラボノイドとギンコライドを含み、脳血流を増加させることで認知機能をサポートします。脳への酸素と栄養の供給を促進し、集中力や記憶力の基盤を整えます。
DHA・EPA - 脳の構造的サポート
オメガ3脂肪酸(DHA・EPA)は、脳細胞膜の重要な構成成分です。脳血流の改善に加えて、βアミロイドの蓄積抑制やBDNF(脳由来神経栄養因子)の増加により、長期的な脳健康をサポートします。
ウコン(クルクミノイド)- 脳の抗炎症
クルクミノイドは、脳内の慢性炎症を抑制し、神経細胞の健康を維持します。特に還元型クルクミノイド(ホワイトクルクミノイド®)は、従来のクルクミンより高い生体利用効率と抗酸化作用を持ちます。
ムクナ抽出物(L-DOPA)- モチベーションの向上
ムクナ抽出物は、ドーパミンの前駆体であるL-DOPAを含みます。やる気や動機に関わる神経伝達物質ドーパミンの材料となり、モチベーションの維持と向上をサポートします。
高麗人参 - 疲労回復とストレス軽減
高麗人参の有効成分ジンセノサイドは、疲労回復、血行促進、ストレスの軽減、不眠の予防・改善などの効果が期待できます。
GABA(ギャバ)- ストレス緩和
GABAは、γ-アミノ酪酸の略でアミノ酸の一種です。脳や脊髄に存在し、神経伝達物質としてストレスや緊張を緩和します。脳の興奮を鎮め、血圧を下げ、睡眠の質を高める役割があります。
認知機能サプリメントの選び方:5つの重要ポイント

市場には数多くの認知機能サプリメントがありますが、以下のポイントを押さえて選ぶことが重要です。
1. 科学的エビデンスの有無
信頼のおけるエビデンスがある成分を選ぶのがおすすめです。一方で、根拠のない効果を謳っているものはお勧めしません。
医学研究等に興味がある方であれば、すこし難易度は高いですが、ランダム化比較試験(RCT)やメタアナリシスなど、信頼性の高い研究によって効果が実証されていることを調査するのもよいでしょう。
※なお、本記事で紹介した成分は、いずれも複数の査読済み研究論文で効果が確認されています。
2. 有効成分の配合量
科学的研究で効果が示された成分であっても、その研究で用いられた「有効量」に達していなければ、同様の効果は期待できないからです。
残念ながら、市場には「〇〇(注目成分)配合!」と謳いながら、実際には効果を実証するには不十分な量しか含まれていない製品もあります。
信頼できる製品を見極めるには、本記事の前半で解説したような臨床試験で実際に使われた量を参考にしましょう。以下に、主要な成分について、多くの研究で有効性が確認されている1日あたりの摂取量の目安をまとめました。製品の成分表示と照らし合わせてみてください。
◎ Neumentix®:持続的注意力や作業記憶の改善を目指す研究では、300mg〜/日の摂取が基準とされています。
◎ α-GPC:認知機能サポートを目的とした研究では、100mg〜/日の範囲で用いられることが一般的です。
◎ ホスファチジルセリン(PS):記憶に関する複数の研究で、80mg〜/日の摂取で肯定的な結果が報告されています。
◎ L-テアニン:リラックス効果やストレス軽減を目的とする場合、80mg〜/日が一般的な有効量とされています。
◎ Zynamite®:精神的疲労の軽減や反応速度の向上に関する研究では、150mg〜/日の摂取が採用されています。
これらの数値はあくまで目安ですが、製品選びの際の重要な判断基準となります。成分表示を確認し、有効量がしっかりと配合されている製品を選ぶようにしましょう。
3. 原料の品質と規格
ブランド原料(Neumentix®、Suntheanin®、LIPAMIN PS™など)は、厳格な品質管理と標準化がなされており、信頼性が高いです。一般的な原料名だけでなく、具体的なブランド名が明記されている製品を選びましょう。
4. 安全性の確認
GRAS認定(一般的に安全と認められている)を取得している成分や、長期使用の安全性試験が実施されている成分を選びましょう。アスリートの方が摂取する場合には、アンチドーピング認証(BSCG認証など)の有無も重要なポイントになります。
5. 相乗効果を考えた複合配合
単一成分よりも、複数の成分を組み合わせた製品の方が、多角的なアプローチにより高い効果が期待できます。たとえば今回ご紹介した成分であれば、以下のような組み合わせがあります。
- ・α-GPC + ホスファチジルセリン:アセチルコリン供給と細胞膜環境の最適化
- ・L-テアニン + カフェイン:興奮と鎮静のバランス
- ・Neumentix® + Zynamite®:持続的な集中力と精神的疲労の軽減
安全性について:知っておくべきこと
一般的な安全性
本記事で紹介した成分は、いずれも長期使用の安全性試験が実施されており、重篤な副作用の報告はほとんどありません。軽微な体調変化(軽度の消化器症状、一過性の頭痛など)が報告されることはありますが、摂取中止に至るケースは極めて稀です。
注意すべき点
- 妊娠・授乳中の方:安全性データが限定的なため、医師に相談してください
- 医薬品との相互作用:血圧降下薬や睡眠薬などとの相互作用の可能性があります
- 過剰摂取:推奨量を守り、過剰摂取は避けてください
- アレルギー:大豆由来成分(PS、レシチンなど)にアレルギーがある方は注意が必要です
重要:本記事の内容は、科学的研究に基づく情報提供を目的としており、医学的アドバイスを意図するものではありません。特定の健康状態については、必ず医療専門家にご相談ください。
まとめ:科学的根拠に基づく認知機能サポートを
認知機能サプリメントは、適切に選択・使用することで、記憶力、集中力、学習能力などの認知機能を効果的にサポートできます。重要なのは、科学的エビデンスに基づいた成分を、有効量で継続的に摂取することです。
本記事で紹介した主要成分をまとめます:
| 成分名 | 主な効果 | 推奨量 |
|---|---|---|
| Neumentix® | 持続的注意力向上、記憶力改善 | 300mg〜/日 |
| α-GPC | アセチルコリン前駆体、学習能力向上 | 100mg〜/日 |
| ホスファチジルセリン | 記憶機能改善、実行機能向上 | 80mg〜/日 |
| L-テアニン | リラックスした集中、ストレス軽減 | 80mg〜/日 |
| Zynamite® | 精神的疲労軽減、反応時間短縮 | 150mg〜/日 |
これらの成分を効果的に組み合わせることで、単一成分では到達できないレベルの認知機能向上が期待できます。
PPNが提案する認知機能サプリメント

思考・感情・行動を一点に集中させる「超集中モード」へ
本記事で詳しく解説した主要成分をすべて、科学的エビデンスに基づく有効量で配合。私たちPPNが開発した111'NEURO DRIVEは、9種類の認知機能向上成分を独自の黄金比で配合したヌートロピックサプリメントです。
配合成分
Neumentix® / Zynamite® / α-GPC / LIPAMIN PS™ / Suntheanin® / イチョウ葉エキス / DHA・EPA / ホワイトクルクミノイド® / ムクナ抽出物
✓ BSCGドーピング検査認証取得(全ロット検査済み)
✓ 30件以上の査読済み研究論文に基づく配合設計
✓ 医薬品レベルの品質管理基準で製造
✓ アスリート、ビジネスマン、クリエイターなど多くの方が愛用
参考文献
Falcone, P. H., et al. (2019). The attention-enhancing effects of spearmint extract supplementation in healthy men and women. *Nutritional Research*, 64, 24-38.
Herrlinger, K. A., et al. (2018). Spearmint Extract Improves Working Memory in Men and Women with Age-Associated Memory Impairment. *Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 24(1), 37-47.
Kato-Kataoka, A., et al. (2010). Soybean-derived phosphatidylserine improves memory function of the elderly Japanese subjects with memory complaints. *Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition*, 47(3), 246-255.
Wightman, E. L., et al. (2020). Acute Effects of a Polyphenol-Rich Leaf Extract of Mangifera indica L. (Zynamite) on Cognitive Function in Healthy Adults: A Double-Blind, Placebo-Controlled Crossover Study. *Nutrients*, 12(8), 2194.
Hidese, S., et al. (2019). Effects of L-Theanine Administration on Stress-Related Symptoms and Cognitive Functions in Healthy Adults: A Randomized Controlled Trial. *Nutrients*, 11(10), 2362.