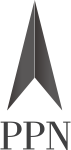「筋トレで脳が成長する」──そんな話を聞いたら驚かれるでしょうか?
実は最新の研究により、ウエイトトレーニングなどの無酸素運動でも、脳の成長因子であるBDNF(脳由来神経栄養因子)が増加することが明らかになってきました。
これまでBDNFの増加といえば、ランニングやサイクリングなどの有酸素運動が定番でした。しかし、近年の複数の研究を統合したメタ分析では、レジスタンストレーニング(筋トレ)がBDNFレベルを調整する上で最も効果的な運動である可能性も示唆されています 。
本記事では、筋トレがどのようにして脳機能を向上させるのか、その科学的メカニズムと実践方法を、具体的な研究結果を交えながら詳しく解説します。「体を鍛えながら頭も良くなる」──そんな一石二鳥のトレーニング法を、ぜひ最後までご覧ください。

株式会社ピークパフォーマンスニュートリション(PPN)
代表取締役
パワーリフティングジム TXP代表(公式HP)
NPO法人東京都パワーリフティング協会 副理事長(公式HP)
元パワーリフティング選手(2023年11月の世界選手権を最後に引退)
2010年~2023年105kg級日本代表(2021~2023年団長)
2012~2023年全日本選手権12連覇
NSCA-CPT(2001年取得)
NSCAストレングス&コンディショニングスペシャリスト(2004年取得)
公認スポーツメンタルコーチ


現在プライベートでは東京都立大学大学院人間健康科学研究科において認知運動制御研究の第一人者の樋口貴広教授の元で研究生活を送っている。
BDNFとは?脳の成長を促す「魔法の物質」

BDNF(Brain-Derived Neurotrophic Factor:脳由来神経栄養因子)は、脳の神経細胞の成長、生存、機能維持を促進する重要なタンパク質です。1982年に発見されて以来、「脳の肥料」とも呼ばれ、認知機能や精神健康に深く関わることが明らかになってきました。
BDNFの主な働き
- 神経新生の促進:特に記憶を司る「海馬」での新しい神経細胞の生成を促す
- シナプス可塑性の向上:学習と記憶の基盤となる神経細胞間の接続を強化
- 神経保護作用:酸化ストレスや炎症から神経細胞を保護する
- 神経伝達の最適化:ドーパミンやセロトニンなどの神経伝達物質のバランスを調節
- 認知機能の改善:記憶力、集中力、学習能力の向上に寄与する
BDNFレベルの低下は、うつ病やアルツハイマー病、パーキンソン病などの神経変性疾患と関連することが報告されています (Pałasz et al., 2020)。逆に、生活習慣を通じてBDNFを増やすことで、これらのリスクを低減し、脳の健康を維持・向上させることが期待できるのです。
従来の常識:「BDNFを増やすなら有酸素運動」の理由
これまで、BDNFを増加させる運動といえば、圧倒的に有酸素運動が推奨されてきました。その背景には、多くのシステマティックレビューやメタ分析の蓄積があります。
有酸素運動の優位性を示した研究
例えば、2016年に行われたメタ分析では、2週間以上の運動介入の効果を調べた結果、有酸素運動は安静時の血中BDNF濃度を有意に増加させたのに対し、レジスタンストレーニングでは有意な増加が見られなかったと報告されています (Dinoff et al., 2016)。このような研究結果が、「BDNFを増やすなら有酸素運動」という常識を形成してきました。
実際、中強度の有酸素運動を継続することで、運動直後から数時間にわたり血中BDNF濃度が増加することが多くの研究で確認されています (Huang et al., 2014)。
新たな発見:筋トレでもBDNFは増える!最新研究が示す可能性

しかし近年、研究デザインや対象者を精査することで、レジスタンストレーニングでもBDNFが増加することを示す研究が相次いで発表されています。特に「強度」が重要な鍵を握ることが分かってきました。
筋トレによるBDNF増加のエビデンス
| 研究内容 | 対象 | 主な結果 |
|---|---|---|
| 高強度(80% 1RM) vs 中強度(60% 1RM)の筋トレ | トレーニング経験のある男性 | 80% 1RMのセッション後1時間でBDNFが有意に増加。60% 1RMでは変化なし (Borges Junior et al., 2023)。 |
| 筋トレと有酸素運動の長期的な効果の比較 | 高齢者 | 長期的な介入後、筋トレ群と「筋トレ+有酸素」群でBDNFが有意に増加 (Marinus et al., 2019)。 |
| 高強度 vs 高ボリュームの筋トレ | トレーニング経験のある男性 | 7週間のトレーニング後、強度やボリュームに関わらず、両群でBDNFが増加 (Church et al., 2016)。 |
| 様々な運動タイプの比較メタ分析 | 健常者および非健常者 | レジスタンストレーニングが、他の運動タイプと比較して最もBDNFレベルを改善した (Zhou et al., 2022)。 |
筋トレがBDNFを増やす独自のメカニズム
-
機械的ストレス応答
筋肉への強い負荷が、メカノトランスダクションを介してBDNF産生を促進します。 -
マイオカインの放出
筋収縮により分泌される物質が、脳でのBDNF発現を促進します。近年の研究では、筋肉で産生されるのは成熟BDNFではなく前駆体のpro-BDNFであり、これが運動によって増加することが示されています (Edman et al., 2024)。 -
代謝ストレス
筋トレによる一時的な乳酸の蓄積が、適応反応としてBDNF産生を誘導するシグナルとなります。運動中に乳酸を注入すると、血漿中の成熟BDNFがさらに増加することも報告されています (Edman et al., 2024)。
有酸素 vs 無酸素:BDNF増加効果の比較
では、有酸素運動と無酸素運動(筋トレ)では、どちらがBDNF増加に効果的なのでしょうか?この問いに対する答えは、研究の歴史と共に変化してきました。
重要な発見:研究の変遷
2010年代のレビューでは、有酸素運動はBDNFを増やすが筋トレは効果がない、とする見方が主流でした (例: Huang et al., 2014; Dinoff et al., 2016)。しかし、2020年頃からの新しいメタ分析では、筋トレ、特に適切な強度で行うことで、有酸素運動と同等、あるいはそれ以上にBDNFレベルを調整する上で効果的である可能性が示されています (Zhou et al., 2022)。
結論:「組み合わせ」と「強度」が鍵
これらの研究結果が示すのは、もはや「有酸素か筋トレか」という単純な二者択一ではないということです。適切な強度の筋トレはBDNF増加に非常に有効であり、さらに有酸素運動と組み合わせることで、より包括的な効果が期待できると言えます。高齢者を対象とした研究でも、筋トレ単独、および筋トレと有酸素の組み合わせがBDNF濃度を効果的に増加させたと報告されています (Marinus et al., 2019)。
実践編:BDNFを最大化する筋トレプログラム
では、具体的にどのような筋トレを行えば、効果的にBDNFを増やせるのでしょうか?研究データに基づいた実践的なプログラムをご紹介します。
1. 高強度を意識したレジスタンストレーニング
BDNFの増加には「強度」が重要です。ある研究では、1RMの60%の強度ではBDNFに変化がなかったのに対し、1RMの80%の強度では運動1時間後にBDNFが有意に増加しました (Borges Junior et al., 2023)。
プログラム例
- 種目:スクワット、デッドリフト、ベンチプレスなどの多関節運動
- 強度:1RMの70-85%(「ややきつい」と感じるレベル)
- セット:3-4セット × 6-10回
- 休憩:セット間休憩は60-120秒
- 頻度:週2-3回
このプログラムは、BDNF増加に効果的とされる高強度トレーニングの原則に基づいています。
筋トレ×BDNF効果を最大化する5つのポイント
1. タイミング:朝のトレーニングが効果的か?
朝の運動が日中のBDNFレベルを高く維持し、認知機能の向上に寄与することが示唆されています。また、ストレスホルモンであるコルチゾールの自然な日内リズム(朝に高く夜に低い)と同調することで、より効果的なBDNF産生が期待できるという説もあります。
2. 栄養:BDNF産生をサポートする食事
運動効果を最大化するには、適切な栄養が不可欠です。特にオメガ3脂肪酸、ポリフェノール、ビタミンD、亜鉛、マグネシウムなどは、BDNFの産生や機能に関連する栄養素として知られています。
3. 睡眠:回復とBDNF産生の要
質の高い睡眠(7-9時間)は、運動によるBDNF増加効果を定着させ、最大化します。特に深い睡眠中にBDNFの産生と神経の修復が活発に行われます。
4. ストレス管理:過度なストレスはBDNFを低下させる
慢性的なストレスはコルチゾールを過剰に分泌させ、海馬のBDNFを低下させることが知られています。筋トレは適度なストレスとして機能しますが、オーバートレーニングは逆効果になるため、適切な休息が不可欠です。
5. 継続性:長期的な視点を持つ
運動によるBDNFレベルの変化は、急性(単回)の効果と慢性(長期的)の効果があります。例えば、16週間のレジスタンストレーニングまたは有酸素トレーニングによって、安静時のBDNF濃度が上昇したという報告があります (Freeman et al., 2021)。結果を焦らず、最低でも数ヶ月単位で継続することが重要です。
よくある質問:筋トレとBDNFについて
Q1:筋トレの強度はどのくらいがBDNF増加に最適ですか?
A1:研究データを総合すると、1RMの70-85%程度の高強度が効果的と考えられます。実際に、80% 1RMの強度でBDNFの有意な増加が確認された一方、60% 1RMでは変化がなかったという研究報告があります (Borges Junior et al., 2023)。初心者の方はより低い強度から始め、徐々に強度を高めていくことが安全かつ効果的です。
Q2:有酸素運動と筋トレ、どちらを先にすべきですか?
A2:BDNF増加を最大化する目的であれば、筋トレ → 有酸素運動の順番が効果的である可能性が示唆されています。ただし、これは仮説の段階であり、最も重要なのは両方の運動を継続的に行うことです。高齢者を対象とした研究では、筋トレと有酸素運動を組み合わせたトレーニングがBDNF増加に有効であったと報告されています (Marinus et al., 2019)。
Q3:毎日筋トレをしてもいいですか?
A3:BDNFの観点からは、週2-4回が現実的かつ効果的と考えられます。毎日の高強度トレーニングはオーバートレーニングを招き、コルチゾールの慢性的な上昇を引き起こし、かえってBDNFを低下させるリスクがあります。筋肉と神経系が回復するための休養日を設けることが、長期的な効果につながります。
まとめ:筋トレで体も脳も鍛える新時代へ

本記事で見てきたように、筋トレはBDNFを増加させる有効な手段であることが、近年の質の高い研究によって裏付けられています。特に、適切な強度(70% 1RM以上)で行うことが重要です。
最新のメタ分析では、有酸素運動やHIITなど他の運動と比較して、レジスタンストレーニングが最もBDNFレベルを改善したという報告さえあります (Zhou et al., 2022)。
「有酸素か筋トレか」という二者択一ではなく、それぞれの利点を理解し、両方を組み合わせることが、あなたの脳を最高の状態に保つための鍵となるでしょう。
今すぐ始められる実践ポイント
- 週2-3回、30-60分の筋トレから始める
- 多関節運動(スクワット、デッドリフト等)を中心にプログラムを組む
- 強度は「ややきつい」と感じるレベル(1RMの70%以上)を目指す
- 十分な睡眠と、タンパク質や良質な脂質を含む栄養を摂る
- 結果を焦らず、長期的な視点で継続する
筋トレは、もはや単なる筋肉づくりのためだけではありません。それは脳の成長因子BDNFを増やし、認知機能を向上させ、長期的な脳の健康を守る「究極の脳トレ」でもあるのです。体を鍛えながら頭も冴えわたる──そんな一石二鳥のトレーニングを、ぜひ今日から始めてみませんか?
筋トレ×BDNF効果を最大化するなら:111'NEURO DRIVE

筋トレの効果を脳機能向上につなげる究極のサポート
本記事で解説した筋トレによるBDNF増加効果を、さらに高めたい方へ。私たちPPNが開発した111'NEURO DRIVEは、BDNF増加をサポートする成分を含む9種類の認知機能向上成分を、科学的根拠に基づき最適配合したサプリメントです。
BDNF関連成分を配合
・DHA・EPA(Driphorm® HiDHA360):BDNF遺伝子発現を促進
・ホワイトクルクミノイド®:脳の抗炎症作用でBDNFを保護
・イチョウ葉エキス:脳血流増加によりBDNF産生環境を最適化
✓ BSCGドーピング検査認証取得(全ロット検査済み)
✓ トレーニング前の摂取で集中力とパフォーマンスを最大化
✓ アスリートの実践現場で磨かれた配合設計
主な参考文献
- Borges Junior, M., et al. (2023). Impact of Strength Training Intensity on Brain-derived Neurotrophic Factor. International Journal of Sports Medicine.
- Church, D. D., et al. (2016). Comparison of high-intensity vs. high-volume resistance training on the BDNF response to exercise. Journal of Applied Physiology.
- Dinoff, A., et al. (2016). The Effect of Exercise Training on Resting Concentrations of Peripheral Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF): A Meta-Analysis. PLoS ONE.
- Edman, S., et al. (2024). Pro-Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF), but Not Mature BDNF, Is Expressed in Human Skeletal Muscle: Implications for Exercise-Induced Neuroplasticity. Function.
- Freeman, A., et al. (2021). Resistance Or Endurance Training Increases Brain-derived Neurotrophic Factor Concentrations In Middle Age Females. Medicine & Science in Sports & Exercise.
- Huang, T., et al. (2014). The effects of physical activity and exercise on brain-derived neurotrophic factor in healthy humans: A review. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.
- Marinus, N., et al. (2019). The Impact of Different Types of Exercise Training on Peripheral Blood Brain-Derived Neurotrophic Factor Concentrations in Older Adults: A Meta-Analysis. Sports Medicine.
- Pałasz, E., et al. (2020). BDNF as a Promising Therapeutic Agent in Parkinson’s Disease. International Journal of Molecular Sciences.
- Zhou, B., et al. (2022). Effects of different physical activities on brain-derived neurotrophic factor: A systematic review and bayesian network meta-analysis. Frontiers in Aging Neuroscience.
本記事の内容は、科学的研究に基づく情報提供を目的としており、医学的アドバイスを意図するものではありません。特定の健康状態については、必ず医療専門家にご相談ください。また、トレーニングプログラムを開始する前には、必ず専門のトレーナーや医師に相談し、個人の体力レベルに応じた適切な指導を受けることをお勧めします。