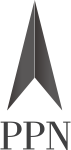運動中の栄養補給は特に運動時間の長い競技においてはパフォーマンスを左右する主要因の一になります。近年,特にトライアスロンやマラソン,長距離サイクリングのような持久系競技において,「単位時間あたりの糖質の吸収量を最大化する」ため,次の2つの方法に注目が注がれています(Jeukendrup 2017)。その背景にあるのが,"gut saturation"――つまり腸の吸収限界という概念です。
・腸の吸収限界(gut saturation)の回避
・胃腸管トレーニング
今回のブログでは前者に着目しご紹介いたします。
腸の吸収限界とは何か?:gut saturationの概念整理

一般的に,体内に貯蔵されているグリコーゲンは約600g程度(体格,食事内容,体力レベル,最近の運動状況によって大きく変動)とされています(Murray and Rosenbloom 2018)。高強度の持続的運動ではおよそ1.5〜2時間程度で枯渇します。それゆえ,特にトライアスロンやマラソン,長距離サイクリングのような競技においては,単位時間あたりにどれだけ効率よくエネルギーを取り込めるかが,後半のパフォーマンスを大きく左右します。
どれだけ糖質を摂取しても,それが腸で吸収されなければエネルギーにはなりません。逆に,吸収できなかった糖質が腸内に残ると,消化器トラブルの原因にもなりかねません。たとえば,運動中の腹部膨満感,胃の不快感,下痢などの症状は,吸収限界を超えたことによって起こる典型的な問題です。これは特に,炎天下や高強度での長時間運動,または水分摂取と炭水化物摂取を同時に行う状況で起こりやすく,レースや試合中のパフォーマンスに致命的な影響を与える可能性があります。
今回のテーマでは,この「腸の吸収限界」に着目し,運動中のエネルギー戦略として,どのような補給が競技タイプによって適しているのかを考えていきます。
異なる輸送体(運び屋)を利用する
腸の吸収限界,いわゆる"gut saturation"とは,小腸における糖質の輸送キャパシティを超えたときに起こる現象です。代表的な糖質であるグルコースは,SGLT1というトランスポーター(運搬役)を介して吸収されますが,グルコースは一度に吸収できる量に限界があります。おおよそ1時間あたり60g程度が限界とされており,それ以上のグルコースを摂取しても,吸収されずに残ってしまうリスクがあります。
この限界を乗り越える手段として注目されているのが,異なる輸送体を活用した複数糖質の併用摂取です。GLUT5という別のトランスポーターはフルクトースの吸収を担っており,グルコースとフルクトースを併用することで吸収経路を分散できます。その結果,1時間あたり90g以上の糖質吸収が可能になるという報告もあります((Fuchs et al. 2019)。この研究ではグルコースとフルクトースを1.2 g/minと0.8 g/minの比率(約3:2)で同時に摂取しています。このような複数輸送体の活用は,近年多くのスポーツ栄養論文でも再注目されています。
これらの戦略は,補給量をただ増やすのではなく,「異なる経路をどう同時に使うか」という腸内吸収のマネジメントに他なりません。特に長時間の持久系競技においては,吸収量の最大化がパフォーマンスに直結します。エネルギーの持続供給が途切れることなく続くことで,運動後半でも安定したパフォーマンスを発揮できる可能性が高まります。
ここで1つ,分かりやすいアナロジーをご紹介します。糖質の補給と吸収を「駅に人を運び込むバス」に例えてみてください。グルコースだけで補給するのは,1本のバス路線にすべての乗客を集中させるようなもの。一定の時間内に乗れる人数には限界があります。でも,別の路線(=フルクトースの輸送路)を使えば,より多くの人を駅(=血流)に運ぶことができます。つまり「異なる路線=異なる輸送体」を使うことで,同じ時間でもより多くの糖質を体内に届けられるのです。
異なる輸送経路をフル活用して単位時間あたりの糖質の吸収量を最大化するコンセプトは,弊社で開発しているタンパク質の摂取を最大化するためにペプチドと遊離アミノ酸を同時摂取する戦略と似ています(製品00X’,001’3.1)。ジペプチドはペプチドトランスポーターとい輸送体で運搬され,アミノ酸はアミノ酸トランスポーターという輸送体で運搬されます。ちなみにタンパク質の輸送の場合はペプチドトランスポーターの方が一度に運搬できるアミノ酸量も多く,輸送速度も速いという特徴があります。最近では遊離アミノ酸以上にアミノ酸が二つ結合したジペプチドに注目が注がれています(Paulussen et al. 2021)。
輸送経路をフル活用するコンセプトは今後の栄養補給戦略の一つの柱となっていくでしょう。
競技によって異なる「補給の正解」

一方で,すべての競技において「吸収量の最大化」が最適とは限りません。たとえば,サッカー,ラグビー,テニス,短距離サイクリスト,
さらに,糖質とタンパク質を同時に摂取することで,インスリン分泌が促進され,結果的にグリコーゲン再合成速度が高まることも知られています。これは運動後の回復戦略として特に有効であり,1日に複数セッションをこなす競技者にとっては極めて重要な意味を持ちます。
「筋肉のパフォーマンスを保つ」という点では,エネルギーだけでなく材料の供給も必要です。車で言えば,ガソリン(糖質)を補給するだけではエンジン内部の摩耗には対応できません。そこにオイル(タンパク質)が加わってはじめて,エンジン(筋肉)は長く高出力を保てると考えてもいいかもしれません。
個人的には「グルコースとフルクトースを同時摂取する」戦略を採用している選手もタンパク質(ペプチドか遊離アミノ酸)を少しでも添加することでさらなパフォーマンスアップを期待できる可能性があるのではないかと考えています。もちろんその際は消化吸収の必要のないタンパク質の形態を選択するのがベストと考えられます。
製品設計に見る,腸吸収限界と選択のバランス
我々PPNでは,この吸収限界の視点と競技特性を踏まえたうえで,糖質とタンパク質を約3.7:1の比率(Saunders et al. 2004)で配合したサプリメント「00X’AAA+ALPHA」を開発しています。使用している糖質は,高分子構造で胃滞留が少なく,吸収効率に優れるクラスターデキストリン1種類です。
クラスターデキストリンは,従来のマルトデキストリンやグルコースに比べて,胃から小腸への排出が早く,かつ浸透圧も低いため,運動中の胃腸への負担が少ないのが特徴です。これにより,運動中の補給による消化器ストレスを軽減しながら,安定したエネルギー供給を可能にしています。
さらに,タンパク質については,吸収スピードと利用効率を最大化するため,先述したペプチドトランスポーターとアミノ酸トランスポーターの両方を利用できるよう,加水分解処理されたホエイペプチドを採用しています。これは,タンパク質におけるgut saturationという限界を避けつつ,筋肉の出力と回復を両立させる実戦型の戦略です。
00X’AAA+ALPHAのコンセプトは,「腸でいかに効率よく吸収させるか」「その先でいかに即効性のある形で筋肉へ届けるか」にあります。多くのプロ選手が採用する理由は,数値化されにくい“感覚としての疲労”の軽減を実感しているからです。
我々が知っておくべき“戦略的補給”の視点
ここで強調しておきたいのは,糖質の「摂取量」だけを考えるのではなく,「吸収量」「同化効率」「回復の質」まで視野に入れるべきだということです。特に「自分の腸が吸収できるかどうか」は見落とされがちで,盲目的に高糖質を摂ってトラブルにつながる例も少なくありません。
胃腸トラブルの回避は,そのまま「競技を完遂できるかどうか」に関わる要因です。また,タンパク質の混合による補給戦略は,エネルギーの即時供給と同時に,筋肉ダメージのコントロールにも直結します。
そして最も重要なのは,「どちらが正解か」ではなく,「自分の競技にはどちらが適しているのか」を理解し,選択する視点です。マラソン選手にはgut saturation回避が重要でも,ラグビー選手には糖質+タンパク質による筋保護の方が有効かもしれません。ここに個別化された補給戦略の必要性があります。
この“個別化”の考え方は,最新のスポーツ栄養学でも中心的なキーワードになっています。同じ糖質摂取量でも,それを“どう吸収し,どう使うか”は人によって異なります。だからこそ,自分の競技スタイル・身体の感覚・消化吸収の得意不得意を踏まえて,「自分だけの戦略」を築くことが求められています。
まとめ:あなたの競技に合った吸収設計を
gut saturationの回避は,特定のエリート持久系アスリートだけの話ではありません。運動中に「何を,どのように吸収できるか」という戦略は,すべての競技者にとって重要です。
・糖質を最大限吸収し,長時間の出力を維持するのか? ・糖質+タンパク質で,出力と回復の両立を図るのか?
その問いに対する答えは,競技特性,体質,目的によって異なります。今の自分にとっての最適な選択は何か──ぜひ一度,立ち止まって考えてみてください。
格闘技,サッカー,ラグビー,テニス,サイクリスト,ハードトレーニング愛好家のような「断続的,高出力かつ持久的」な運動様式を実践する選手におすすめ|認証済みのサプリメント
00X’AAA+ALPHA

00X’AAA+ALPHAは、限界までの運動持続時間をさらに延長してトレーニングを積みたい方におすすめのサプリメントです。中〜長時間の激しい練習や補強トレーニングを行う際の専用のエルゴジェニックエイドサプリメントです。
限界を超えたトレーニングをサポート、さらにリカバリーにも役立ちます。
引用・参考文献一覧
Fuchs CJ, Gonzalez JT, van Loon LJC (2019) Fructose co-ingestion to increase carbohydrate availability in athletes. Journal of Physiology-London 597:3549-3560 doi: 10.1113/jp277116
Jeukendrup AE (2017) Training the Gut for Athletes. Sports Med 47:101-110 doi: 10.1007/s40279-017-0690-6
Liang YH, Chen Y, Yang F, Jensen J, Gao RR, Yi LY, Qiu JQ (2022) Effects of carbohydrate and protein supplement strategies on endurance capacity and muscle damage of endurance runners: A double blind, controlled crossover trial. Journal of the International Society of Sports Nutrition 19:623-637 doi: 10.1080/15502783.2022.2131460
Murray B, Rosenbloom C (2018) Fundamentals of glycogen metabolism for coaches and athletes. Nutrition Reviews 76:243-259 doi: 10.1093/nutrit/nuy001
Paulussen KJM, Alamilla RA, Salvador AF, et al. (2021) Dileucine ingestion is more effective than leucine in stimulating muscle protein turnover in young males: a double blind randomized controlled trial. Journal of Applied Physiology 131:1111-1122 doi: 10.1152/japplphysiol.00295.2021
Saunders MJ, Kane MD, Todd MK (2004) Effects of a carbohydrate-protein beverage on cycling endurance and muscle damage. Medicine and Science in Sports and Exercise 36:1233-1238 doi: 10.1249/01.Mss.0000132377.66177.9f
禁止薬物違反は致命的|安心できるアンチドーピング認証商品を選ぼう
ドーピング検査は、抜き打ちで行われます。今まで陰性であっても、サプリメントを変えたり増やしたりしたことで、ドーピング違反になるリスクはすべてのアスリートにあるといってよいでしょう。
ドーピング違反が検出されると、どんな場合でも選手の自己責任とされ、長期間の出場停止や資格停止期間が設けられ、取り返しのつかない大きなダメージを受けます。サプリメントを使用する際は、長い目で考えてトレーナーや医者に確認をしたり講習を受けたりして慎重に選ぶべきでしょう。アンチドーピング認証を受けた商品は、比較的安心です。
ただし、パッケージにアンチドーピングと書いてあっても認証マークがないのは検査してない可能性大なので注意が必要です。第三者機関のマークがあるか確認して製品を選んでください。
PPNのサプリメント管理体制につい ー 2つの徹底ポイントのサプリメント管理体制について

・全製品・全ロットを対象に「出荷前」に検査を実施
→検査結果を確認するまで一才出荷しません(圧倒的安全性の確立)
・世界で最も検査項目数が多いBSCG(Banned Substances Control Group)を採用
→業界2位の検査項目数を誇る機関より約25%も検査項目数の多い,国際的に信頼されているBSCGで全商品の検査を実施しています。
摂取によるアンチドーピング規則違反からアスリートを守る唯一の方法、それは、全製品の、全ロットを、市場に流通させる前に検査を実施することです。
市場に流通させながら全ロット検査を実施しているメーカーはいくつかありますが、アスリートのドーピング陽性リスクを極力排除するためには、全ロット検査でも十分ではないと考えています。
そのため、PPNでは全製品・全ロットに対して、市場に流通させる前に検査を実施するだけでなく、「結果を確認するまで出荷しない」という管理体制を取っています。
この体制を取っているメーカーは世界で唯一弊社しかありません。アスリートにとって栄養摂取は投資であり、ドーピング検査の徹底は保険です。PPNでは「体感」と「安全性」を実現できる製品開発に尽力しています。詳しくはこちら>>